こんにちは、キャリアと組織の未来をつなぐ人、尾形ヒロカズです。
「うちのチーム、誰も本音を言わなくなってきた気がする」
「会議で問いかけても、沈黙ばかり」
こんな声を、研修先の管理職や人事担当の方からよく聞きます。
そして、そんなときに出てくるキーワードのひとつが「心理的安全性」です。
最近では、この言葉が企業の中でもかなり浸透してきました。Googleの研究結果などをきっかけに、「心理的安全性が高い職場は成果も高い」というイメージが広がっています。
でも実際には、心理的安全性を「優しい雰囲気」と同義で捉えてしまったり、「否定しなければいい」という表面的な理解にとどまってしまったりする場面も少なくありません。
今日は、そんなちょっとズレた心理的安全性への向き合い方と、黙ってしまうチームに実際に効いた3つの問いかけについて、私自身の現場経験からお話ししたいと思います。
優しい空気が、かえって沈黙を生むこともある
ある企業の研修で、チームの関係性について話していたときのこと。
「うちのチームは仲はいいけど、全員が当たり障りないことしか言わない感じなんです」
という声が出ました。
メンバー同士はトラブルもなく、むしろお互いに配慮しすぎるくらい。でも、その結果として本音や改善提案が出づらくなっていたのです。
これは、衝突のなさ=安全性の高さではないということを表しています。
表面的には波風が立っていなくても、心の中では「何を言っても意味がない」「変に思われたら嫌だ」という不安を抱えているとしたら、それは心理的安全性が高いとは言えません。
むしろ、表面的な安心感が自分の意見を引っ込める要因になってしまうこともあるのです。
心理的安全性=「率直さへの許容」
心理的安全性とは、「この場で話しても大丈夫だ」「自分らしくいられる」と感じられる状態のこと。
そのためには、やさしさよりも率直さのほうが大切です。
もちろん、言い方やタイミングの配慮は必要ですが、
- 「それ、ちょっと違うと思います」
- 「こうしたほうがよくないですか?」
といった意見が出ても、誰かの立場や評価が脅かされない。
そんな「率直な言葉がちゃんと届く」関係性こそが、心理的安全性の本質です。
黙るチームに効いた3つの問いかけ
実際に私が関わった現場で、沈黙がちだったチームに効果があった問いかけをご紹介します。
① 「もし〇〇さんがいなかったら、どうなってたと思う?」
あるメンバーに対して、他のメンバーがどう感じているかを引き出す問いです。
これは、評価や貢献をその人の前で言葉にすることで、空気が一気に和らぎます。
その後、「あ、こういうこと言っても大丈夫なんだ」と思えるようになり、率直なフィードバックが増えていきました。
② 「この案、10点満点でいうと何点ですか?」
意見を聞くとき、「どう思いますか?」だと漠然としすぎて黙ってしまうことも。
でも、点数で評価するようにすると、ちょっと不満はあるけど言いづらいを表現しやすくなります。
「7点くらいですかね」といった発言から、「どこが引っかかりますか?」と具体的な対話につなげやすくなります。
③ 「このやり方にもやっとした人、正直に手を挙げてみてください」
一度、「不満を出しても責められない」空気をつくるための問いです。
特に、全員がやや遠慮しがちなときには、あえてもやもやを前提にした問いで、本音を引き出しやすくします。
すると、「実は少し思ってました…」という声がポロポロ出てきて、話が動き出すことがあります。
安心とは、表面的な「優しさ」ではない
心理的安全性という言葉が一人歩きし、「怒らない」「否定しない」「笑顔でいる」といった表面的な要素だけを満たしてしまうと、逆に本音が出ない空気になってしまいます。
大事なのは、率直であっても大丈夫だという安心感です。
だからこそ、「どうすれば言える空気になるか?」という問いに、チームごとに取り組んでいく必要があります。
その一歩として、今回紹介したような問いの工夫が、沈黙の空気をゆっくりほぐしてくれるかもしれません。
読んでくださり、ありがとうございました。
心理的安全性は、単なる「優しさ」ではなく、率直な意見や本音が出せる関係性の土台です。
もし今、チームや職場の「沈黙」や「本音の出づらさ」に課題を感じている方がいれば、よろしければ一度ご相談ください。
現場に合わせた心理的安全性の醸成や、対話の仕掛けづくりを、具体的な実践を交えながらご支援しています。
▼ リベラキャリアへのお問い合わせはこちら

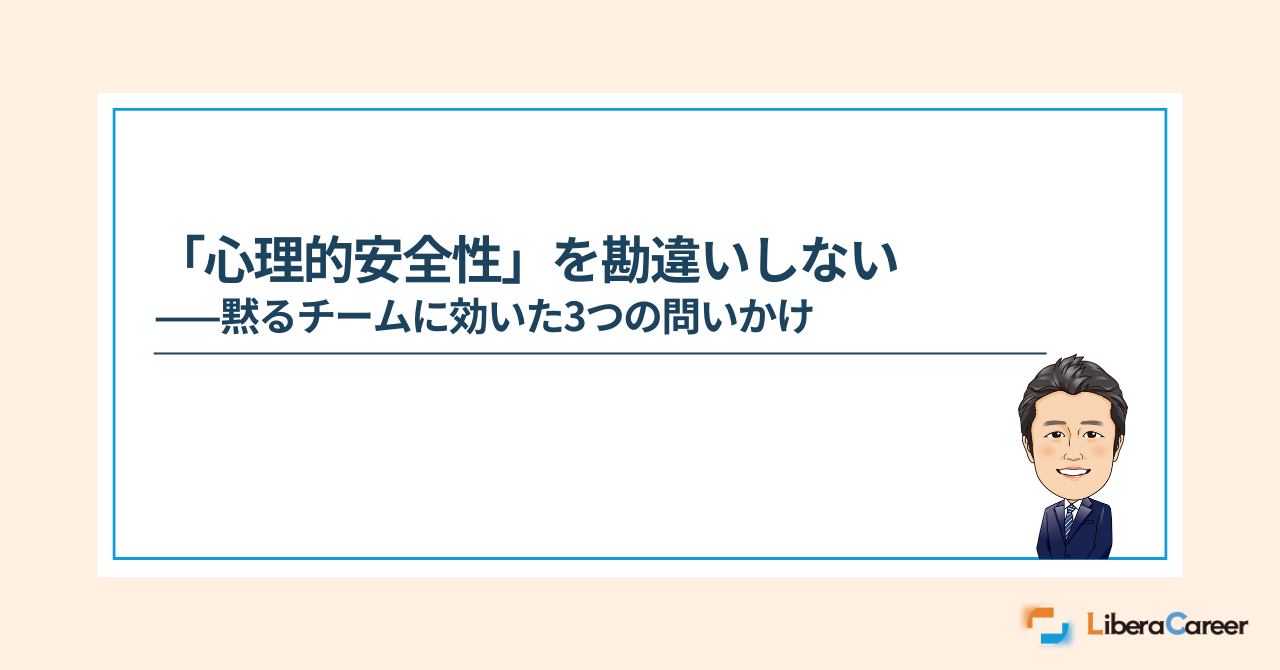
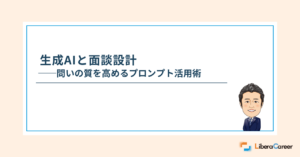
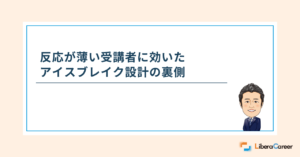
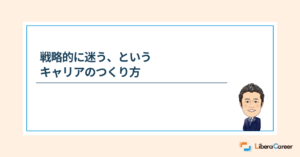
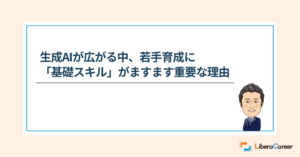
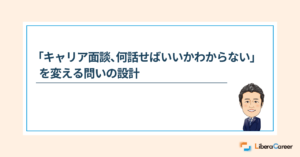
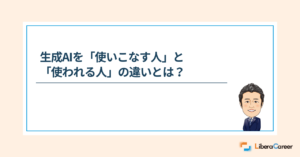

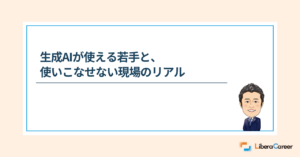
コメント