あなたの研修、それ、AIが代わりにやっても変わらないかもしれませんよ?
…ちょっとドキッとする問いかけから始めてしまいましたが、これは冗談でも煽りでもありません。
実際、ChatGPTなどの生成AIの登場によって、情報提供型の研修の価値はどんどん相対的に下がってきています。
スライドを読み上げるだけの研修なら、AIでもできてしまう。むしろAIのほうが早口じゃないし、脱線もしないかもしれません。
じゃあ、我々人間の講師にしかできないことって何なのか?
なぜ、研修の成果が出ないことが多いのか?
そして、どうすればAI時代でも「リピートされる講師」になれるのか?
そんなことを、私自身の体験も交えながら、前後編にわたってお話ししていきます。
「いい話だったね」で終わる研修の限界
私がキャリア支援や組織研修に関わってきた中で、よく耳にする声があります。
「すごくいい話だった」 「勉強になった」 「なんかモチベーションが上がった気がする」
……でも、そう言ってくれた方が、1ヶ月後に何を変えたかというと──何も変わっていなかったりします。
これは講師側にも、受講者側にも原因があります。 が、一番大きな理由は、「行動変容につながる設計になっていない」こと。
その背景には、よくある研修設計の落とし穴があります。
- 内容が多すぎて、情報が右から左に流れてしまう
- 業界や職種に合わない例え話で、受講者の共感を得られない
- 話すことに集中しすぎて、受講者の様子を見ていない
実はこれ、AIで自動生成された講義資料を、そのまま喋っているだけの研修にもありがちな構造なんです。
「生成AI × 講師」は最強のはずなのに、なぜ失敗するのか
実は私も、一度やらかしています。
ChatGPTで作ったスライド原稿があまりに美しくて、「これは便利だ!」と、感じました。
若干の違和感。でも、時代の流れもあるし、ある程度は受け入れた方が良いかもしれない、慣れることも必要かもしれない、と、テストケースの意味合いも持ちながらそのまま活用。
もちろん、これは、無料セミナーで試しました。お客様を巻き込むわけにはいきません。
結果として、
実際のセミナーでは、反応が鈍い。どこかしっくりこない。
なぜか?
理由は明白で、「その会社や受講者のリアル」が抜けていたからです。
受講者はロボットじゃありません。業界、職種、会社の文化、直面している課題、それぞれ全然違う。
AIは確かに情報を整理するのは得意。でも、“現場のリアル”をすくい上げるには、やはり、限界があります。
だからこそ、講師がその現場に寄り添って、「あ、この人、自分たちのことをちゃんと見てくれてる」と思わせられるかが、AI時代における大きな差別化ポイントになるんです。
AIを使いこなす講師に必要なのは「設計と編集」
私は今、「AIは準備で使う、場では人が活きる」と思っています。
- テーマの整理
- 情報の取捨選択
- ワーク案のブラッシュアップ
こうした“事前準備”ではAIはとても有効。
でも、最終的に「どこを話すか」「どう届けるか」「どこを削るか」は人の仕事。
つまり、AI時代に求められるのは「話す力」ではなく、「設計と編集の力」なんです。
後編では、実際に私が生成AIを活用しながら「リピートされた」研修設計の事例をご紹介します。
AIを使ったからこそ伝わったこと、逆にAIに頼らなかったからこそ響いたこと──
その境界線を、一緒に探ってみませんか?
リベラキャリアでは、生成AIを活用した研修をはじめ、キャリア開発・心理的安全性・ハラスメント防止・若手育成・管理職研修など、企業の課題に合わせた多様なテーマでの研修をご提供しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

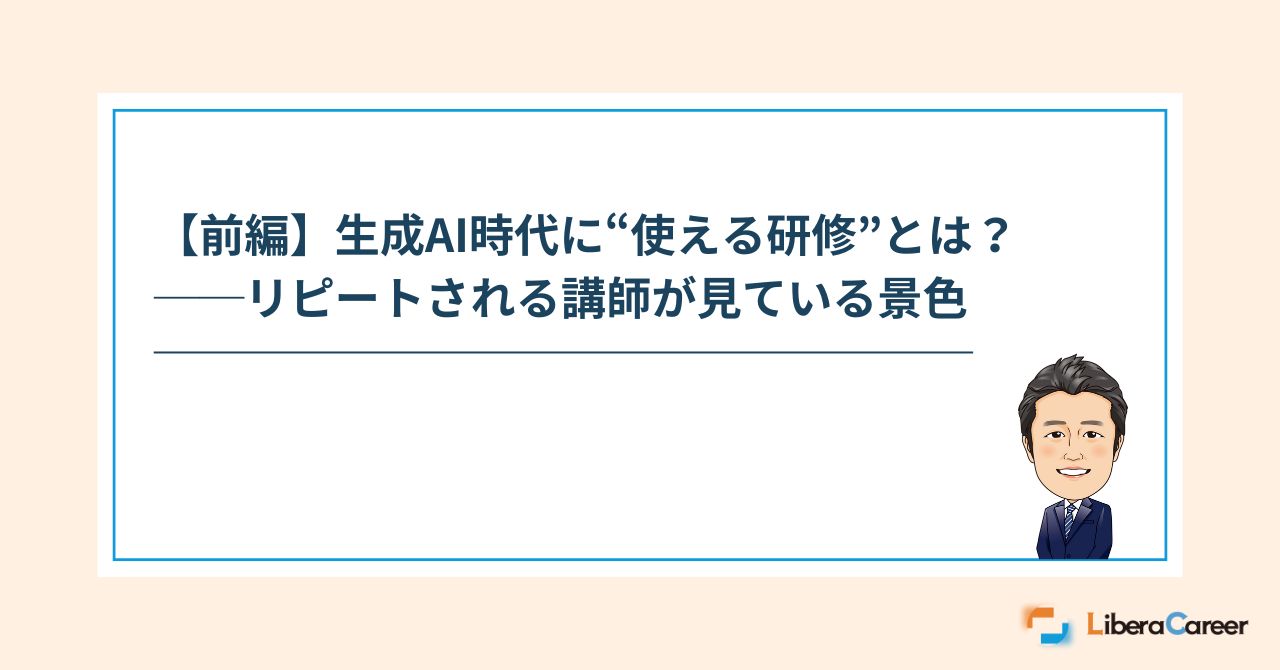
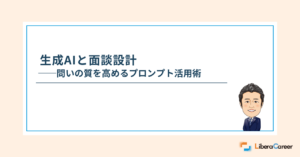
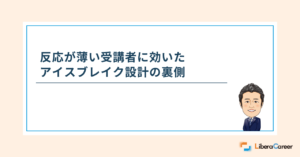
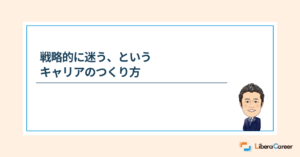
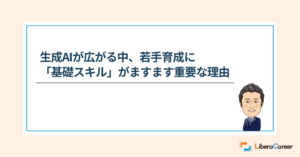
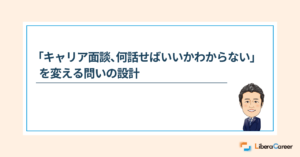
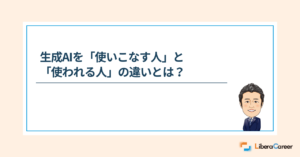

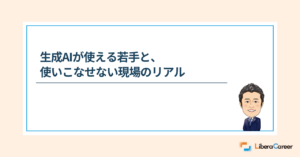
コメント