こんにちは、キャリアと組織の未来をつなぐ人、尾形ヒロカズです。
「若手の定着や育成が思うように進まない」という相談を人事や管理職の方からよく受けます。
どんなに丁寧に研修をしても、現場に戻った途端にうまくいかなくなる。 声をかけているつもりなのに、相手との距離が縮まらない。
そんなとき、うまくいっているチームの特徴を思い出すと、ある共通点が見えてきます。
今回は、私がこれまで現場で見てきた中で、育成がうまくいくチームが必ずやっていることを紹介します。
チーム運営に悩む方や、現場の支援を担当する人にとって、ヒントになれば幸いです。
1. フィードバックを相手目線で設計している
うまくいっているチームでは、指導のタイミングや言い方が絶妙です。
その理由は、相手がどんな気持ちでその日そこにいるのか、を想像しているからです。
たとえば、
- 最初から具体的に伝えすぎない
- あえて問いで返す
- やらなかった理由を責めず、まず受け取る
こうしたフィードバックの仕方には、相手の緊張や不安に共鳴しようとする姿勢があります。
相手が心を閉じてしまえば、どんな正論も届きません。 だからこそ、言葉を選ぶだけでなく、届き方まで考えることが、育成の質を左右します。
2. ちょっとした声かけを日常にしている
育成がうまくいくチームは、特別な1on1や評価の場面だけでなく、 日常のすき間にこそ、コミュニケーションのチャンスがあると考えています。
- 出勤時に「昨日の資料、分かりやすかったよ」とひと言添える
- 打ち合わせ前に「無理してない?」「最近どう?」と軽く聞く
- 報告を聞いたあとに「その視点、ありがたい」と気づきを伝える
こうした声かけの積み重ねが、信頼残高を増やすのです。 信頼があるからこそ、厳しいことも伝えられるし、相手も受け取ってくれる。
3. 一人で育てようとしない仕組みを持っている
現場の育成がつまずく大きな要因の一つが、特定の人に任せきりになっていることです。
- 指導担当が変わると、方針も伝え方もリセットされる
- 担当者が多忙で、育成に手が回らなくなる
こうした状態を防ぐために、うまくいっているチームは次のような工夫をしています。
- 最低限の育成方針をチーム内で共有しておく
- 教える内容やフィードバック例を簡単に記録する
- ペアを固定せず、複数人で関わるようにする
チーム全体で育てるという視点があることで、属人化を防ぎ、継続的な育成が可能になります。
4. 育つ側の気持ちをチームで言語化している
育成がうまくいっているチームには、育つ側の感情や立場への想像力があります。
たとえば、
- 覚えることが多すぎて焦っているかも
- 初対面の人ばかりで、緊張しているかも
- ここにいていいのかなと感じているかも
こうした前提を持って関わることで、行動が変わります。
- 一気に説明せず、段階的に渡す
- 雰囲気を和らげる声かけを先にする
- わからないことを聞きやすい空気を意識してつくる
これはマニュアルではカバーできない、人に向き合う姿勢です。
最後に:育成は、スキルより習慣で差がつく
育成のノウハウは、今やさまざまな媒体で学ぶことができます。
でも実際に現場で差がつくのは、スキルの有無ではなく、日々のちょっとした習慣の違いです。
- ひと言添えるかどうか
- 相手の顔を見る時間を取っているか
- 伝えたではなく届いたかを気にしているか
これらの積み重ねが、育つ人の意欲や信頼を左右します。
特別なテクニックよりも、目の前の一人ひとりに対しての丁寧な関わりを。
その習慣こそが、育成がうまくいくチームの共通点です。
読んでくださり、ありがとうございました。
育成は「誰か一人が頑張るもの」ではなく、チーム全体の関わり方で変わっていきます。
もし今、若手の定着や育成に悩まれている方がいれば、よろしければ一度ご相談ください。
現場に合わせた育成の仕組みづくりや、心理的安全性の土台づくりを、現場目線でご一緒しています。
▼ リベラキャリアへのお問い合わせはこちら

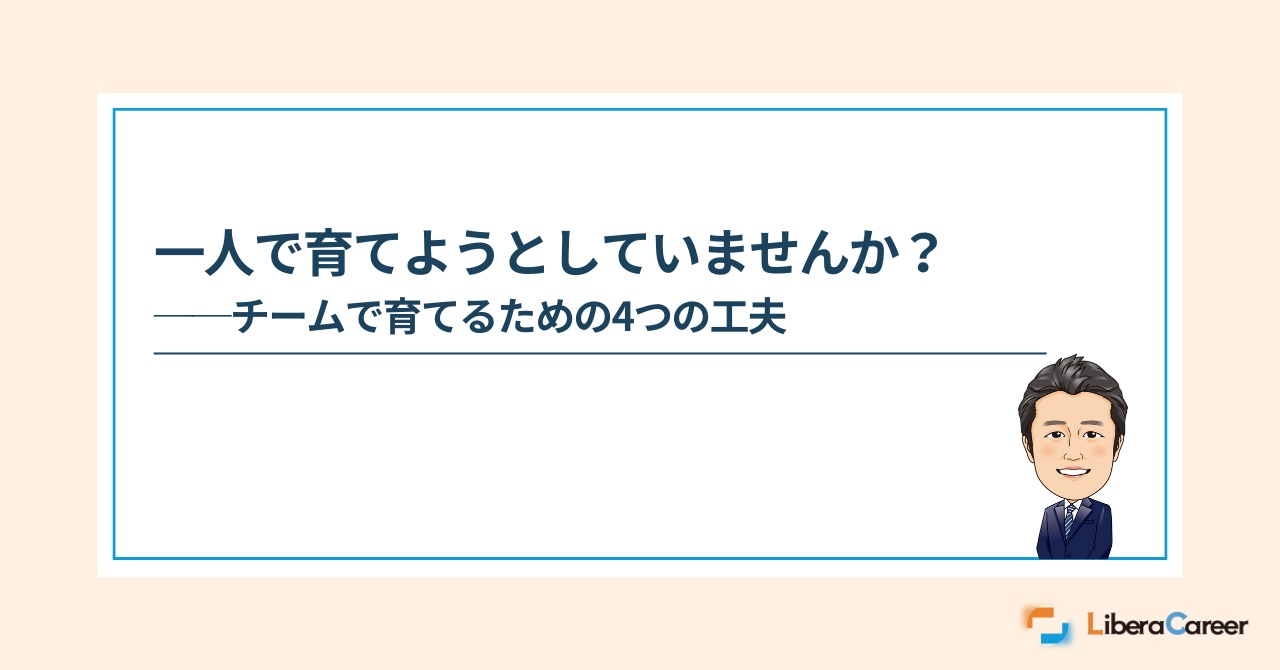
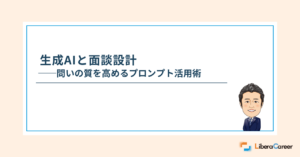
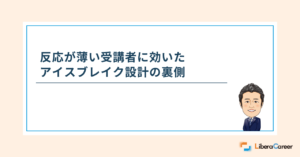
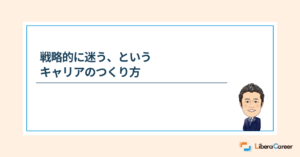
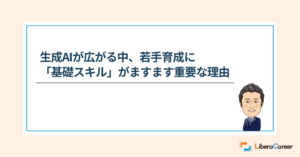
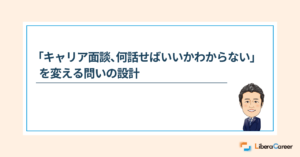
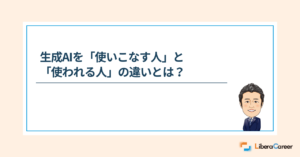

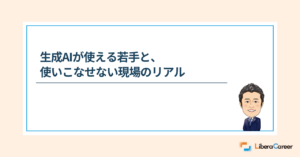
コメント