こんにちは、キャリアと組織の未来をつなぐ人、尾形ヒロカズです。
最近、企業の研修や支援の現場で、こんな声をよく聞きます。
「若手は生成AIを自然に使いこなすけど、現場では活かしきれない」
「AI活用の話になると、ベテラン層やマネジメントが置き去りになる」
「便利だとは思うけど、実際の業務でどう落とし込めばいいのかがわからない」
生成AIが話題になる一方で、職場では使える人と使いこなせない現場のギャップがじわじわと広がっています。
この違和感を放置すると、単なるITスキルの話にとどまらず、組織内のコミュニケーションや働き方にも歪みを生んでいきます。
今回は、そんな現場のリアルと、そこから見えてきたヒントについてまとめてみます。
目次
- 若手は試せるけど、現場は失敗できない
- 現場の不安は技術より責任にある
- AI活用を現場に浸透させるための視点
- 技術だけではなく、関係性も変えるチャンス
若手は試せるけど、現場は失敗できない
若手社員の中には、生成AIをツールの一つとして軽やかに試している人が増えています。
- ChatGPTで文章のたたき台をつくる
- 生成画像で資料を彩る
- アイデア出しにAIを使う
こうした使い方は、彼らにとっては特別なことではなく、スマホやPCと同じ日常ツール感覚に近いものです。
一方で、現場の実務やマネジメントの立場になると、
- 顧客対応や品質管理に関わる
- 誤情報や誤解を避けなければならない
- 結果に対する責任が重い
といった背景があるため、簡単に試せない、失敗できないという空気が根強くあります。
その結果、生成AIの活用は若手の自己流にとどまり、現場全体に広がらないというギャップが生まれるのです。
現場の不安は技術より責任にある
このギャップの背景にあるのは、単なるITリテラシーの問題だけではありません。
むしろ現場で強く感じるのは、間違ったらどうしようという責任感や不安感です。
- お客様に間違った情報を伝えたら
- 誤字脱字や表現ミスが増えたら
- AI頼みの仕事だと評価が下がるのでは
こうしたリアルな不安が、生成AI活用のブレーキになっている現実があります。
だからこそ、単純に便利だから使いましょうと言うだけでは、現場は動きません。
AI活用を現場に浸透させるための視点
生成AIを現場に活かすためには、次のような視点が欠かせません。
① 小さな成功体験を積ませる
いきなり全業務で使うのではなく、
- 社内の文章チェック
- アイデア出しの補助
- 会議議事録の整理
など、リスクの少ない場面から使い、効果と安心感を積み上げていくことが重要です。
② 成果と責任の線引きを共有する
AIが出した答えをそのまま使うのではなく、
- 最終チェックは人が行う
- 誤解を生まない表現に整える
- AI補助ありと透明性を持たせる
といったルールを明確にすることで、責任の所在があいまいになる不安を減らせます。
③ 若手とベテランの教え合い文化をつくる
若手が得意なAI操作と、ベテランが持つ業務知識や判断力を組み合わせることで、世代間の得意不得意を補い合う風土が生まれます。
技術だけではなく、関係性も変えるチャンス
生成AIは、単なる便利ツールではなく、働き方や組織の関係性を見直すきっかけにもなりえます。
- AIをきっかけに、世代間の壁をゆるめる
- 新しい働き方の実験を小さく始める
- できないが言いやすい空気をつくる
そんな工夫を重ねることで、現場に根づくAI活用が少しずつ進んでいきます。
生成AIを味方につけるのは、若手だけの特権ではありません。
責任のある現場ほど、慎重さと柔軟さを両立させながら、一歩ずつ進めていくことが大切だと感じています。
読んでくださり、ありがとうございました。
生成AIは、ただの「便利なツール」ではなく、現場の関係性や働き方に変化をもたらすきっかけになります。
でも実際には、「失敗できない現場」や「責任の所在が不明確な状況」が、活用を難しくしているのも事実。
だからこそ、まずは小さな実験から。
世代を超えた協働や、安心して試せる仕組みづくりが重要です。
もし今、生成AIの現場活用や、社内への浸透方法に課題を感じている方がいれば、よろしければ一度ご相談ください。
現場の不安に寄り添いながら、最初の一歩を一緒に設計いたします。
▼ リベラキャリアへのお問い合わせはこちら

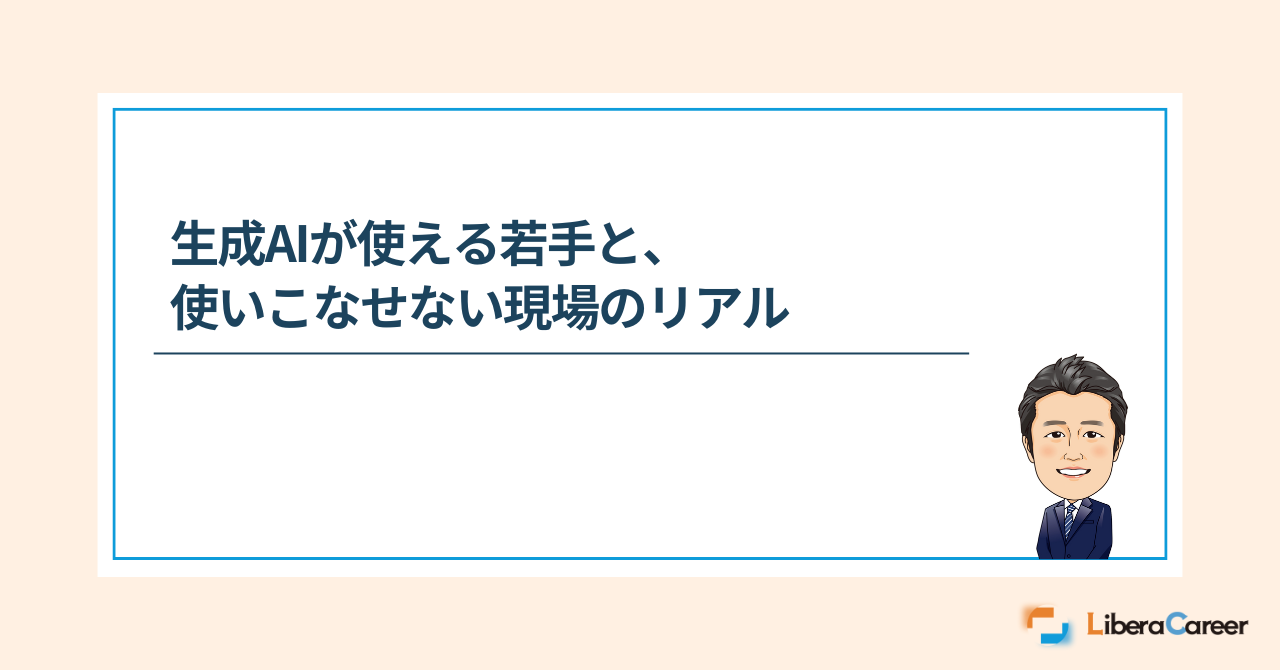
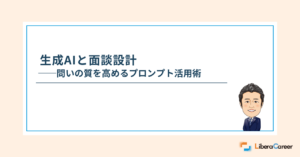
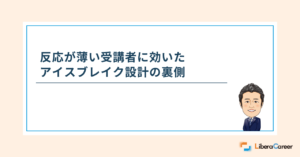
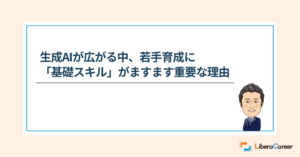
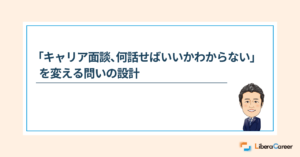
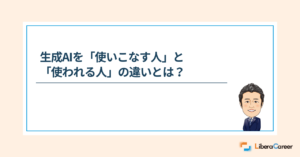

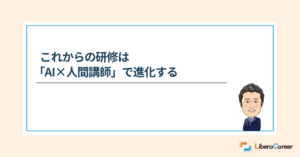
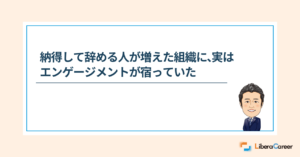
コメント