こんにちは、キャリアと組織の未来をつなぐ人、尾形ヒロカズです。
最近、多くの企業現場でこんな声を聞きます。
- 若手がChatGPTをうまく使っていて驚いた
- ドキュメントの下書きや、企画案のたたき台をAIで作っている
- 「このままいくと、経験の少ない人でも十分やっていけるのでは?」
たしかに、生成AIの進化は目覚ましく、今後も活用の幅は広がっていくでしょう。
しかし、だからこそ今あらためて問いたいのが、「人としての基礎スキル」の重要性です。
目次
- なぜ今、「基礎スキル」が見直されるのか
- 現場で起きている「見えない分断」
- 基礎スキルをどう育てるか
- ● フィードバックの「言語化」を促す
- ● グループでの「比較と対話」の場をつくる
- キャリアの「足腰」は、変わらず必要
なぜ今、「基礎スキル」が見直されるのか
生成AIが「できること」は、着実に増えています。
情報の整理、文章の構成、メール文案、企画書の骨子…
これまでは時間をかけて習得していたスキルの一部が、簡単に出力できるようになりました。
でも、それを「使いこなす」ためには、前提としての人間側の力が必要です。たとえば:
- 目的に応じて情報を取捨選択する論理的思考力
- 他者とすれ違わずに働くための対人スキル(報連相・感情調整)
- 成果物をよくするためのフィードバックの受け止め力・発信力
これらは、生成AIが代替するのが難しい、人間の「地力」の部分です。
現場で起きている「見えない分断」
実際、AIを活用して仕事を進める若手が増える一方で、
それを見て「中身が浅い」「考えていない」と感じる上司とのすれ違いが起きています。
- 上司:「もう少し自分で考えてから持ってきてほしい」
- 若手:「でも、AIでこれくらいは出るんですよね…」
このギャップは、単なる世代間の感覚差ではありません。
「生成物の質」と「思考過程の深さ」が一致しない時代が来ているということです。
だからこそ、育成の現場では、「成果物だけを見て評価する」だけでは不十分になりつつあるのです。
基礎スキルをどう育てるか
では、こうした背景の中で、若手にどんな育成の機会が必要なのでしょうか。
ポイントは、「使うこと」だけでなく、「使ったあとに考えること」にあります。
以下のような設計が有効です:
● フィードバックの「言語化」を促す
生成AIで作成した成果物について、「なぜこの構成にしたか」「どこに迷ったか」「他に考えた案は?」などを問い、思考過程をアウトプットさせる時間をとる。
● グループでの「比較と対話」の場をつくる
同じお題に対して、各自がAI+自分で作った案を持ち寄り、どこが違うか、どこが優れているかを共有し合う。
- 人間の判断が必要な部分はどこか?
- なぜ自分はこの案に納得できたのか?
こうした内省と言語化の反復が、「基礎スキル」の筋トレになるのです。
キャリアの「足腰」は、変わらず必要
AIの進化によって、「とりあえずやってみる」「形にしてみる」ことのハードルは確実に下がっています。
でも、その次の一歩を踏み出すには、
- 相手の意図を汲み取る読解力
- 自分の考えを伝える表現力
- 視点を切り替える柔軟性
といったキャリアの足腰とも言える力が必要です。
どんなに便利な道具が出てきても、それを「何のために、どう使うか」を判断するのは、やはり人です。
そして、その判断には、日々の積み重ねの中でしか育たない「基礎スキル」が根っこにあるのだと思います。
読んでくださり、ありがとうございました。
生成AIが急速に広がる今だからこそ、「基礎スキル」をどう育てるかが、若手育成の質を左右します。
ツールを“使う力”だけでなく、“使ったあとに考える力”を育てること。
それが、AI時代における人材育成の本質だと感じています。
もし今、若手育成やAI活用の研修設計に課題を感じている方がいれば、よろしければ一度ご相談ください。
AI時代に必要な「考える力」を育む仕組みづくりを、現場の実践知からサポートしています。
▼ リベラキャリアへのお問い合わせはこちら

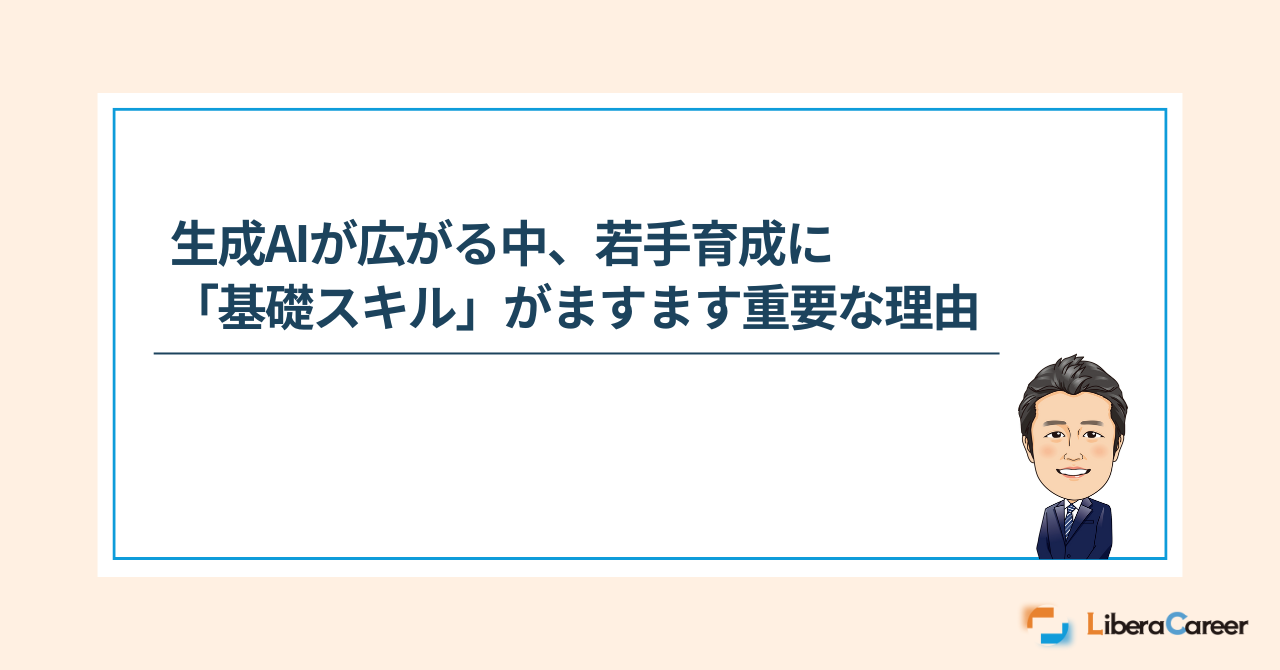
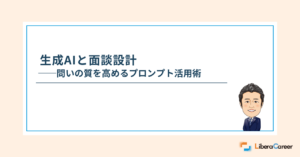
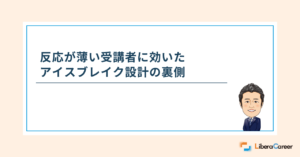
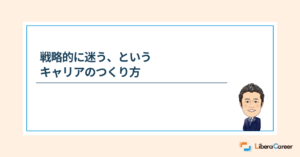
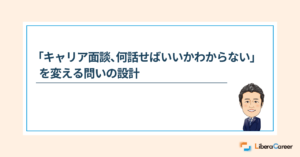
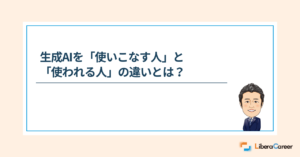

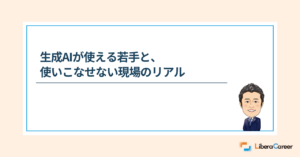
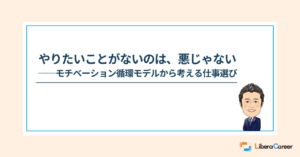
コメント