こんにちは、キャリアと組織の未来をつなぐ人、尾形ヒロカズです。
「せっかく時間もコストもかけて実施した研修なのに、現場に戻ったら元どおり」
そんな声を、現場の人事担当やマネージャーの方からたびたび耳にします。
一方で、似たテーマ・対象でも、明らかに「定着する研修」と「その場限りで終わる研修」があるのも事実。
何が違うのか?どこで差がつくのか?
今回は、私が企業研修や現場支援の中で実践してきた中から、研修を「やって終わり」にしないために設計段階で押さえておきたい5つの原則を紹介します。
1. 「なぜやるのか」を最初に丁寧に共有する
参加者の意欲と行動変容は、「意味の納得」から始まります。
研修の冒頭では、研修テーマが現場でどんな課題と関係しているのか、参加者自身にどんな影響があるのかを、具体的に言語化して伝えましょう。
目的をスライドにまとめるだけではなく、講師や登壇者の言葉で「なぜこの場が必要なのか」を語ることが鍵です。
2. 現場の「あるある」から設計する
汎用的なスキルや知識も大切ですが、現場のリアリティに即していないと「自分ごと」になりません。
成功している研修は、対象者が実際に直面している悩みや困りごと、もしくはよくある言動や会話から構成されています。
「よくこんなやり取りしませんか?」
「こんな場面で戸惑ったことないですか?」
こうした入り口から入ることで、参加者の「経験の棚卸し」と結びつき、学びの定着率が格段に上がります。
3. 対話・内省を必ず組み込む
知識提供だけで終わると、研修は受け身の時間になってしまいます。
重要なのは、インプットとアウトプットのバランスです。
ワークやグループ対話を通して、「自分はどうだったか」「どんな変化が必要か」を内省する時間を設けましょう。
この時間があることで、参加者は研修内容を「借り物の言葉」ではなく、「自分の経験」とつなげて整理できるようになります。
4. 研修後の行動にブリッジをかける
研修で気づきや学びがあっても、現場に戻ったときにどうやって実行に移すかが曖昧だと、行動に結びつきません。
有効なのは、小さな一歩を具体的に決めることです。
「来週のチームMTGでこれを試してみよう」
「○○さんにこんな声かけをしてみる」
このような「今の仕事にどう取り入れるか」を最後に整理する時間をとることで、現場へのつながりが生まれます。
5. 上司や周囲との連携を設計段階から考える
参加者が研修でどれだけ意欲を持っても、戻った職場に理解やサポートがないと、学びが活かされにくくなります。
定着する研修の裏には、上司や周囲が「何を期待されているか」を把握しているという共通点があります。
- 上司向けの事前・事後レクチャーを用意する
- チームでの振り返りを推奨する
- 成果指標と連動させたフォロー体制を整える
こうした工夫があると、参加者も「やって終わり」でなく、職場での実践に向けた後押しを得ることができます。
最後に:設計がすべてを決める
研修の成果は、当日の講義だけで決まるわけではありません。
- どんな入口をつくるか
- どこまで“自分ごと化”できるか
- 終わったあと、どんな行動につながるか
このすべてを、設計の段階で考えておくこと。
それが、研修を「やって終わり」にしないための土台になります。
読んでくださり、ありがとうございました。
「やって終わり」にならない研修は、設計段階の工夫で決まります。
もし今、研修の成果や定着に課題を感じている方がいれば、よろしければ一度ご相談ください。
現場のリアリティや組織の課題に合わせて、成果につながる研修設計をご一緒させていただきます。
▼ リベラキャリアへのお問い合わせはこちら

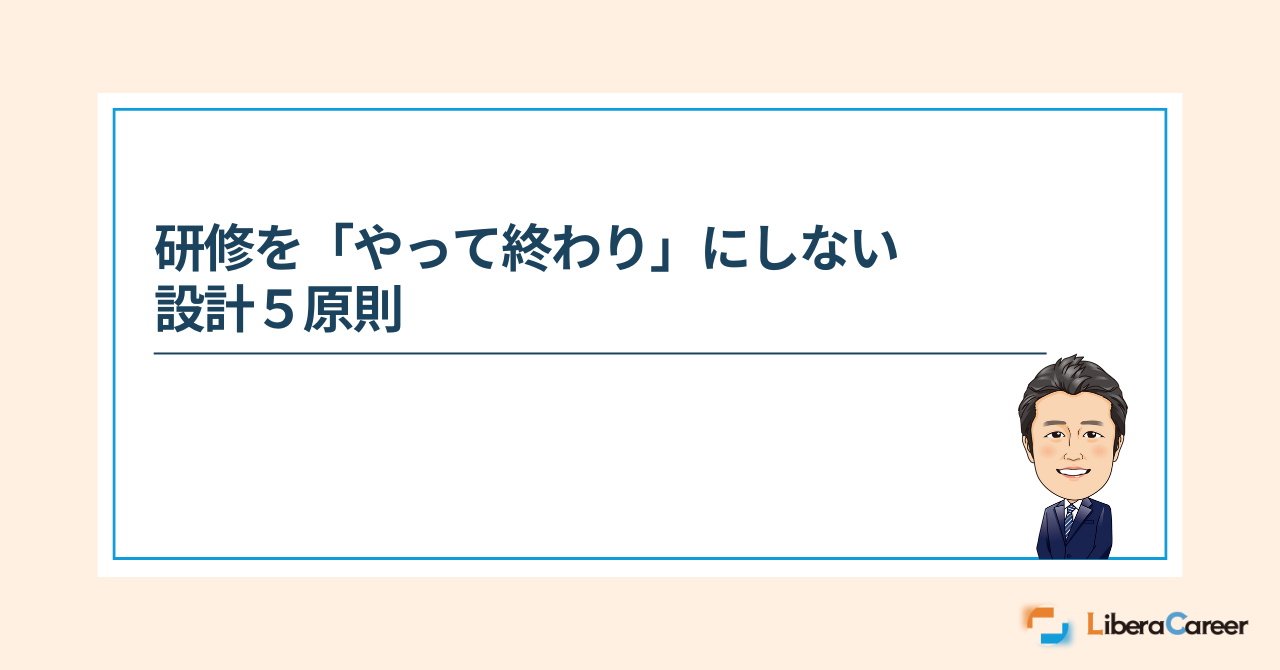
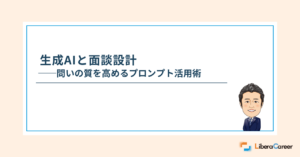
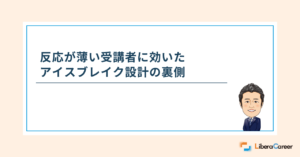
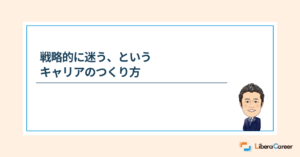
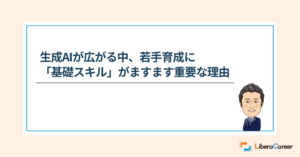
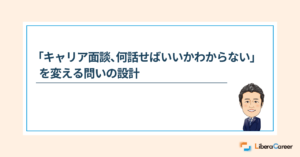
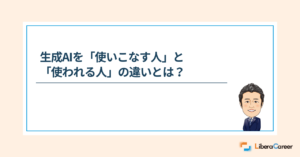

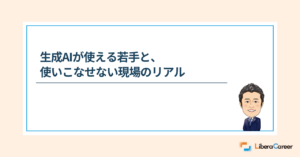
コメント